テレビで「子ども1人を育てるのに3,000万円かかる」と聞いたとき、正直、私は衝撃を受けました。
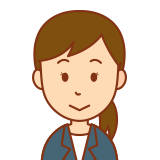
「そんなにかかるの!?」「みんなどうやって用意してるの?」
頭の中は疑問でいっぱい。
お金の勉強をしたほうがいいのかな、誰かに相談すべきかな…
今まで何も考えてこなかった自分に、少し焦りを感じました。
でも実は…
この「3,000万円」という数字は、あくまで最大級の目安なんです。
養育費(食費・服・医療費・習い事など)と、教育費(幼稚園〜大学までの授業料や学校関連費用)をすべて合算し、しかも私立多め・習い事多め・一人暮らし込みという条件で試算した金額です。
例えば…
- 公立中心+自宅通学 → 約800万〜1,000万円
- 私立中心+習い事多め → 約2,000万〜3,000万円
一度に3,000万円が必要なわけではなく、20年以上の長い期間で少しずつかかるのが実情。
さらに最近は幼保や高校授業料の無償化などで、実際の負担は減ってきています。
ですが、この数字のカラクリを知っても、まだまだ不安が尽きない人も多いはず。
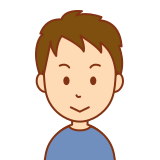
「じゃあ、うちの場合は具体的にいくらかかるの?」
「どうやって準備したらいいの?」
そんな疑問に答えるために、これから具体的にかかる金額と、ムリなく備える方法を分かりやすく解説していきます。
子育てにかかるお金は大きく2種類
子育てにかかるお金は、ざっくり分けると 「養育費」 と 「教育費」 の2つです。
名前は似ていますが、内容も性質もまったく違います。
養育費(よういくひ)
養育費とは、子どもが生活していくために日々かかるお金のことです。
具体的には、次のような支出が含まれます。
- 食費
- 衣類や靴
- 生活用品(オムツ、文房具など)
- 医療費
- お小遣い
- レジャーや外出費用
労金ブランドの調査によると、養育費は月平均で約6万〜9万円程度かかります。
年間にすると約72万〜108万円です。
【参考:実際いくらかかるの?子どもの養育費と教育費|ろうきんブランドサイト】。
養育費は教育費のように「何年後にまとめて必要になる」性質ではありません。
毎月コツコツと家計から支出するため、一気に大きな額を準備する必要はないのが特徴です。
とはいえ、長い期間で見ると総額は大きくなります。
家計の中で「固定費」としてしっかり把握し、無駄を減らす工夫をしておくと安心です。
※最近は物価高が続いているのでもう少し負担は多くなると思います。
教育費(きょういくひ)
教育費とは、子どもが学校に通うために必要な費用全般を指します。授業料や教科書代だけでなく、制服・通学費・部活動費など、幅広く含まれます。
教育費の全体像(幼稚園〜大学まで)
※文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」、日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査」をもとに作成。
| 進路パターン | 幼稚園〜高校 | 大学(4年間) | 合計 |
|---|---|---|---|
| 全て公立+国公立大学 | 約596万円 | 約481万円 | 約1,077万円 |
| 全て公立+私立大学(文系) | 約596万円 | 約690万円 | 約1,287万円 |
| 全て公立+私立大学(理系) | 約596万円 | 約822万円 | 約1,418万円 |
| 全て私立+国公立大学 | 約1,976万円 | 約481万円 | 約2,457万円 |
| 全て私立+私立大学(文系) | 約1,976万円 | 約690万円 | 約2,666万円 |
| 全て私立+私立大学(理系) | 約1,976万円 | 約822万円 | 約2,798万円 |
公立と私立で大きく差がある
文部科学省「令和5年度 子供の学習費調査」によると、幼稚園〜高校までの年間学習費は以下の通りです。
- 幼稚園
公立:約18万円/私立:約35万円 - 小学校
公立:約34万円/私立:約183万円 - 中学校
公立:約54万円/私立:約156万円 - 高校(全日制)
公立:約60万円/私立:約103万円
(参考:文部科学省 子供の学習費調査PDF)
大学の教育費(国公立・私立別)
日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査」(2021年度)によると、大学4年間(入学金+在学費用=授業料・教材費等)の平均は以下です:
- 国公立大学:約481万円
- 私立大学(文系):約690万円
- 私立大学(理系):約822万円
※【参照】子どもの教育費はいくらかかるのか?-平均額を解説-
進路で変わる総額の差
- 公立中心+国公立大学なら約1,000万円前後
- 私立中心+私立理系大学なら約2,800万円超
- 下宿や一人暮らしをすると+500万円前後かかる場合も
大学の進学スタイルによる負担の違い
実家通学と一人暮らしでは、教育費に加えて生活費や準備費もかかります。
例えば、日本政策金融公庫の同じ調査によると:
- 大学の受験費用:平均約30万円
- 自宅外通学(下宿)にかかる費用(敷金・家財道具など):平均約39万円
- 下宿開始時の初期費用や仕送りなど、意外とまとまった金額が必要である点も注意が必要です
教育費を理解するポイント
- 大きな支出は節目ごとに発生:特に入学・進学のタイミングでまとまった費用が必要。
- 進路によってコスト構造が変化:公立中心か私立中心か、大学の進路によって大きく差が出る。
- 長期計画が欠かせない:早い段階から貯蓄・積立や奨学金制度の活用を考えておくと安心。
養育費は毎月の支出、教育費は未来への投資。
その違いを理解しつつ、具体的な金額を知ることで、家計の計画がグッとリアルになります。
教育費を準備する8つの方法
教育費は数年単位の長期戦になります。
無理なく、計画的に貯めるためには複数の方法を組み合わせるのがポイントです。
自分で用意する
1.預貯金
- 一番シンプルで安全な方法。
- 教育費専用の口座をつくると使い込み防止に効果的。
- 定期預金や積立定期などで自動的に貯まる仕組みを作ると継続しやすい。
2.積立投資(つみたてNISAなど)
- 使うまで10年以上の時間がある場合に有効。
- 年3〜5%程度のリターンを想定すると、同じ金額を貯めても効率が上がる。
- 元本割れの可能性もあるため、短期で使う分は預貯金と分けるのが安心。
人からもらう
3.祖父母からの援助(教育資金贈与の非課税制度)
- 最大1,500万円まで贈与税がかからない特例(※条件あり)。
- 銀行などを通して手続きを行う必要がある。
(参考:国税庁 教育資金の一括贈与非課税制度)
4.児童手当
- 第1子の場合(高校卒業まで支給)
- 0〜2歳:月15,000円 × 36ヵ月 = 54万円
- 3〜18歳年度末:月10,000円 × 180ヵ月 = 180万円
- 合計:234万円
- 第3子以降の場合
- 0〜18歳年度末まで:月30,000円 × 216ヵ月 = 648万円
- 全額を貯蓄に回せば、大きな教育資金の柱になります。
5.修学支援制度
- 所得が一定以下の家庭を対象に、授業料や入学金の免除、返済不要の給付型奨学金を受けられる制度。(参考:文部科学省 高等教育の修学支援新制度)
借りる
6.奨学金(日本学生支援機構など)
- 大学進学時に利用できる。
- 第一種(無利子)と第二種(有利子)があり、卒業後に返済が必要。(参考:日本学生支援機構 JASSO)
7.教育ローン
- 日本政策金融公庫や銀行などが提供。
- 返済期間や金利を事前に確認し、返済シミュレーションを行うことが大切。
その他の工夫
8.費用の平準化と家計見直し
- 大きな出費を一度にしないよう、毎月の積立やボーナス時の臨時入金を組み合わせる。
- 習い事や塾など「本当に必要な支出」を見直すことで、将来の教育費に回せる資金を増やせる。
- 1つの方法だけに頼らず、預貯金+投資+制度活用でバランスよく準備する。
- もらえるお金(児童手当や贈与制度)は計画的に教育費口座へ。
- 借りる場合は返済計画を必ず立てる。
まとめ
養育費は、食費や衣類、日用品など日々の生活の中で必ず発生する出費です。
これは家計簿をつけながら、予算の範囲内で管理していくことが大切。
一方で、本当に大きな負担になるのは教育費です。
入学や進学のタイミングで一度にまとまった金額が必要になるため、必要なときにスムーズに出せる状態にしておくことが重要です。
そのためには、短期的な節約だけでなく、10年以上先を見据えた長期的な準備が欠かせません。
預貯金、積立投資、制度の活用を組み合わせながら、「いつでも必要な分を出せる安心感」をつくることが、家計の安定につながります。
私なりに出した答えは、教育費は“計画的に・複数の方法で”用意していくということ。
これが、将来も今も安心してお金を使える家計づくりへの一番の近道だと思っています。

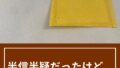
コメント